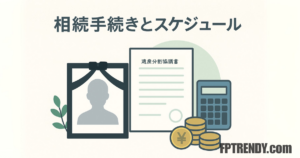✨ 相続対策は「節税のため」だけではない──“思い”を多く残すための第一歩
相続というと、真っ先に気になるのは「税金、どのくらいかかるんだろう?」という現実的な問題。
実際、多くの方が「できるだけ相続税を安くしたい」という思いから、対策を考え始めます。
けれども、節税は単なる“支出の削減”ではありません。
相続税を抑えることで、財産の“手取り”が増えます。
この“手取り”とはつまり、残された家族が使えるお金、守れる資産、実行できる意思──すべてです。
たとえば:
- 節税によって実家を守ることができた
- 子どもに教育資金を残すことができた
- 家業を継ぐための準備資金にあてられた
これらはすべて、被相続人の“想い”が、税金に削られることなく、家族に届いた証です。
💡 相続税は「課税標準 × 税率」で決まる
さて、ここで一度、相続税の仕組みを確認しておきましょう。
本来、相続税はとてもシンプルな構造をしています。
相続税額 = 課税標準 × 税率 − 控除額
この「課税標準」とは、
相続財産の評価額から、基礎控除や債務・葬式費用などを差し引いたあとの課税対象額を指します。
そして、税率と控除額はこの課税標準の額によって決まります。
📌 たとえば…こんな場合
- 課税標準が 2,000万円 の場合
→ 税率:15%、控除額:50万円
→ 計算式:2,000万円 × 15% − 50万円 = 250万円 - 課税標準が 5,000万円 の場合
→ 税率:20%、控除額:200万円
→ 計算式:5,000万円 × 20% − 200万円 = 800万円
このように、課税標準が増えると税率も上がり、控除額があっても税負担は一気に跳ね上がるのです。
だからこそ、**相続対策の鍵は「課税標準をいかに抑えるか」**という点にあります。
✅ 節税=“家族に想いを多く届ける”という選択
節税という言葉には「お金を守る」というイメージが強いかもしれません。
しかし、相続対策における節税は、**“家族に想いを多く届けるための手段”**と捉えるべきです。
手取りが多ければ、多くを引き継げる。
財産が活きて、次の世代の役に立つ。
そして、なにより「ちゃんと残せた」という安心感が、遺された家族の心の支えになります。
次のパートでは、この課税標準を抑えるために「いつ、どんな対策をとるべきか」、
つまり相続対策を“時間軸”で考える意義と実践方法をお伝えしていきます。
🧭 相続対策は「短期・中期・長期」で考える
相続が「いつ起こるか」は誰にも分かりません。
だからこそ、残された時間に応じてできる対策も変わるのです。
この章では、相続対策を「短期」「中期」「長期」の3つに分けて、どんな対策が可能なのかを具体的に紹介していきます。
🕒 短期(相続まで3年以内)──“できることは限られる”からこそ、最小限の手当を
相続が近いと見込まれるとき、
たとえば「最近入院することが多くなった」「財産の名義人が高齢で判断能力に不安がある」──
そんな状況では、スピード重視の対策が求められます。
🔹 たとえば…
- 現金が多ければ、仏壇・墓地の購入や、公益法人への寄付など「非課税財産化」もひとつの手段。
- 賃貸物件を購入して、評価額を圧縮することも検討の余地あり。
- 相続人以外への贈与は、3年以内であれば加算対象になる点には注意!
💡 ポイント:贈与や不動産の名義変更など、税務上「やったことにしておけばいい」という発想は通用しない。正しい手続きと時期が重要です。
📅 中期(3~6年)──“節税と資産活用を両立”できるゴールデンタイム
この時期は、相続がすぐではないが、ある程度予測できる──そんな猶予のある時期です。
資産の組み替えや計画的贈与など、攻めの対策が可能になります。
🔹 たとえば…
- 預貯金を活用して賃貸物件を建築(相続時の評価額は建物分しか課税されない)
- 土地の有効活用(等価交換・用途変更)によって評価額を抑える
- 保険の活用で納税資金を準備
- 小規模宅地等の特例が使えるように、「誰が住むか」を意識しておく
💡 ポイント:「税額を抑える」だけでなく、「家族が活用しやすい形に整えておく」ことが中期対策の肝です。
🧭 長期(7年以上)──“未来を設計する”フェーズ
時間的にもっとも余裕があるこのフェーズでは、制度や仕組みを最大限活用した高度な対策が可能です。
🔹 たとえば…
- 不動産管理会社の設立や公益法人への寄付など、資産を構造的に整理する
- 自社株を複数年に分けて計画的に移転、承継準備を進める
- 信託や養子縁組を通じて、次世代への資産承継ルートを明確にする
- 長期間にわたる贈与(暦年贈与)で評価圧縮&贈与加算対象外に
💡 ポイント:節税だけでなく、“残された家族が困らない設計”ができるのは、この時期しかありません。
✅ まとめ:相続対策は、“時間”が決め手
時間があるからこそ、選べる対策が増える。
時間がないからこそ、優先順位を見誤ってはいけない。
だからこそ、相続対策は「節税テクニック」だけではなく、
“今、どのフェーズにいるのか”を把握することから始めるべきなのです。