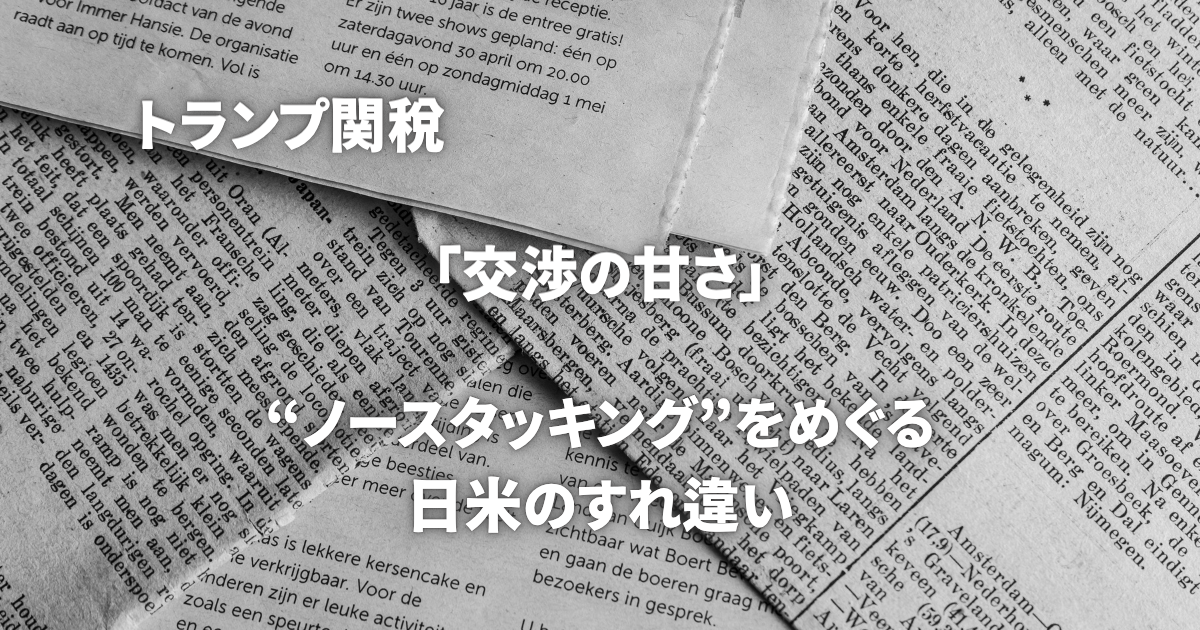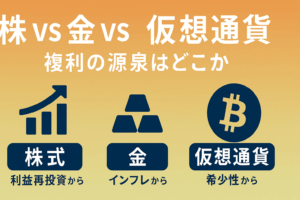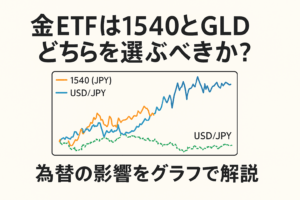2025年8月7日、米国トランプ政権が発動した日本への相互関税。日本政府は「15%の軽減措置が適用された」と説明してきたが、現実には既存関税に新たな15%が上乗せされる“スタッキング課税”が適用された形となった。
その原因はどこにあるのか──。問題の本質は、「ノースタッキング(重複課税なし)」の取り扱いにおける米国と日本の解釈のズレ、そしてその前提となる合意内容の文書化の有無にある。
「ノースタッキング」とは何か?
今回の相互関税における焦点は、「ノースタッキング(No-stacking)」の有無だ。これは、既存関税と新たな関税を単純に加算せず、高い方の税率のみを適用するという方式で、輸出企業の負担を大きく左右する。
たとえば既存関税が7.5%の商品に対して15%の相互関税が導入された場合:
- ノースタッキングあり:15%のまま → 実質7.5ポイントの増税
- ノースタッキングなし:7.5%+15%=22.5% → 実質15ポイントの増税
日本政府は「ノースタッキングが適用される」と主張していたが、実際にはスタッキング(上乗せ)された形で課税が始まっており、織物や一部工業製品の輸出企業に影響が出始めている。
EUとの違い:交渉の“見落とし”か“戦略差”か?
一方、EUは同様の交渉において「ノースタッキング」の適用を明確に主張し、米国側もその原則を一部文書化していた。欧州委員会の記者説明でも、「包括的な15%関税であり、既存関税との重複課税は行わない」と明示されている。
それに対し日本は、「明文化しない明確な合意があった」として交渉を進め、正式な共同声明や議事録を残さなかった。
結果として、米国側が「軽減措置など存在しない」として15%を一律に上乗せする構えを見せても、反論の根拠が日本側に残っていない状況に陥っている。
“交渉の甘さ”という構造的問題
この一連の対応に対し、立憲民主党の野田佳彦代表は「解釈の違いは日本にとって決定的なマイナスだ」と批判。国会でも閉会中審査での政府説明を求める動きが広がっている。
この事態の根底にあるのは、「文書にしないこと」を“迅速さ”と捉えた日本の交渉スタンスだ。赤沢経済再生相は記者会見で、「15%という数字が明確なため、合意文書は不要と判断した」と語っていたが、それが結果的に米国による“都合のよい解釈”を許す余地となった。
国際交渉において「口頭合意」とは、しばしば当事者の主観に依存するものだ。文書によって裏付けされていない“信頼”は、力関係によって容易に塗り替えられる。
今後の教訓とリスク
今回の“ノースタッキング問題”は、通商政策の失敗ではなく、交渉技術と外交スタイルの齟齬による構造的な問題とも言える。
- 書面で確認された合意がなければ、国際政治において“なかったこと”にされる。
- 交渉を急ぎすぎることで、確認や裏付けが甘くなれば、相手の意図次第で意味が変わる。
- 特にトランプ政権のような“既成事実重視”の交渉スタイルに対しては、日本的な「信頼重視」「空気の合意」は通用しない。
「交渉力」とは何かを問い直す
今回の事例が改めて突きつけるのは、交渉力とは、事前の詰めの正確さであり、記録として残す意志であり、想定外を潰しておくことの積み重ねだということだ。
単に「15%で合意した」という事実だけでなく、その運用・定義・適用対象・除外品目・重複課税の有無まで含めて交渉し、それを文章で“ピン留め”しておくこと。それを怠った結果が、今回の関税問題として顕在化した。
おわりに
「交渉の甘さ」とは、交渉担当者個人の過失を責める言葉ではない。むしろ、国家としてどこまで合意の“意味”を詰め切る文化と技術を持ちえているかを問う言葉だ。
交渉の相手が誰であれ、国家の利益を守るには、言葉ではなく記録に残すことが必要不可欠である。そして、それが欠けたとき、失われるのは「信頼」ではなく「既得の利益」なのだ。
【FPTRENDY内部リンク】
【外部関連リンク】
- 日本銀行(BOJ)公式サイト ─ 国内金利や政策決定の確認に。
- 米連邦準備制度理事会(FRB)公式サイト ─ FOMCや声明内容はこちら。
- Bloomberg(ブルームバーグ日本版) ─ 世界の金融・経済ニュースを網羅。
- Reuters(ロイター日本語版) ─ 最新のマーケット速報と経済記事。
- TradingView ─ 株価・為替・指数チャートの可視化に便利。