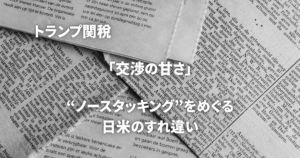はじめに:おとぎ話が経済ニュースに登場?
最近、一部の経済メディアやアナリストのコメントで「ゴルディロックス(Goldilocks)」という言葉が使われているのを見かけることがあります。
たとえば「ゴルディロックス経済」「ゴルディロックス関税」などの表現です。
これは、あの有名なおとぎ話『ゴルディロックスと3匹のくま』に由来する言葉で、「ちょうどよさ」「中間のバランス」を象徴的に表しています。
では、なぜ今この言葉が、トランプ政権の関税政策と一緒に語られているのでしょうか?
ゴルディロックスとはどんな話?
まず簡単におさらいしましょう。
『ゴルディロックスと3匹のくま』は、森のくまたちの家に迷い込んだ金髪の少女ゴルディロックスが、
・「熱すぎる」「冷たすぎる」「ちょうどいい」おかゆ
・「大きすぎる」「小さすぎる」「ちょうどいい」椅子やベッド
を試していくというストーリーです。
この「ちょうどよさ(=中庸)」のイメージが、経済の世界でも好まれる概念となり、「ゴルディロックス経済」という表現が生まれました。
ゴルディロックス経済・ゴルディロックス関税とは?
「ゴルディロックス経済」とは、インフレも失業も低めで、景気が“熱すぎず冷たすぎず”ほどよく安定している状態を指します。投資家にとっては理想的な環境です。
この考え方が派生し、「ゴルディロックス関税」という表現も出てきました。
たとえば、アメリカのVoxは、トランプ政権が打ち出す関税が「高すぎると経済に打撃」「低すぎると効果がない」といったジレンマにあることを取り上げ、「ちょうどよい関税(Goldilocks Tariff)」を探しているようだと表現しました。
でも、「ちょうどよさ」は簡単じゃない
物語の中でゴルディロックスは「ちょうどよい椅子」を見つけたと思ったのに、それが壊れてしまいます。
このエピソードは、「自分にとって快適でも、それが他人や全体にとって良いとは限らない」という教訓として読まれています。
実際の関税政策も同じで、「ちょうどよく見える水準」が、別の誰かの経済活動を圧迫したり、予想外の副作用を生んだりすることがあります。
特にトランプ政権のように政策判断が急変しやすい場合、その“バランス感覚”はますます難しいものになります。
おわりに:なぜ今この比喩が使われているのか
「ゴルディロックス」という言葉が今使われているのは、世界の経済や外交政策が「極端すぎず、穏やかすぎず」という微妙なバランスを求めている時代背景があるからです。
とはいえ、ちょうどよい関税、ちょうどよい金利、ちょうどよいインフレ率──そんな理想の“中間”を見つけるのは、森の中で壊れない椅子を探すのと同じくらい、難しいことなのかもしれません。
【FPTRENDY内部リンク】
【外部関連リンク】
- 日本銀行(BOJ)公式サイト ─ 国内金利や政策決定の確認に。
- 米連邦準備制度理事会(FRB)公式サイト ─ FOMCや声明内容はこちら。
- Bloomberg(ブルームバーグ日本版) ─ 世界の金融・経済ニュースを網羅。
- Reuters(ロイター日本語版) ─ 最新のマーケット速報と経済記事。
- TradingView ─ 株価・為替・指数チャートの可視化に便利。