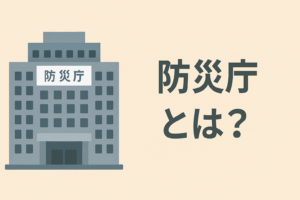はじめに|「不公平だ」と感じたのは関税よりも消費税だった
アメリカのトランプ大統領が推し進める関税強化政策、いわゆる“トランプ関税”が国際社会で大きな議論を呼んでいます。その目的は「不公平な貿易慣行の是正」とされていますが、果たしてその理屈はどこまで通用するのでしょうか。
筆者自身、かつて海外の農産物を輸入して製品を加工製造・販売していた経験があります。その中で、ふと感じたのが「関税よりも消費税のほうが経営には重く響くのではないか?」という素朴な疑問でした。
この記事では、関税と消費税の違い、制度上の公平性、そして実務の現場から見た体感的な“重さ”の差について、冷静に検証してみたいと思います。
輸入農産物には“壁”がある──日本の高関税の実態
日本は農業保護を目的として、農産物に対して世界でも高水準の関税を課している国の一つです。たとえば、米には700%を超える関税が設定されており、乳製品や小麦なども高い税率が維持されています。
果物や加工品などでも10〜30%を超える関税は珍しくありません。筆者がかつて扱っていた輸入農産物も、関税率は20%以上で、仕入れ価格に上乗せされるそのコストは、決して無視できるものではありませんでした。
日本で農業を守るという政策的正当性は理解できるものの、輸入を前提に商売をしている側にとっては、これが一つの“見えない壁”であったことは確かです。
✅ 関税率341円/kg ≒ 最大778%超:事実と根拠
- 日本は世界貿易機関(WTO)の「ミニマム・アクセス枠(MA枠)」外での輸入に対し、341円/キロという高額の関税(specific duty)を課しています。
- これは「アドバルム方式(輸入価格に対して%で課税)」ではなく、重量あたり固定額課税です。そのため、「341円/kg÷国際価格」で計算すると、国内と国際価格の差から導かれる関税率は概ね700〜800%に相当するとされています 。
関税は“痛い”が、売上に対する実効負担は小さい
とはいえ、関税にはもう一つの側面があります。それは、課税のベースが「輸入原価(CIF)」であるという点です。
たとえば、仕入れ原価が100円で関税率が20%の場合、関税は20円となります。しかしこの商品を300円で販売すれば、関税は売上に対して6.7%の負担で済むことになります。つまり、原価が安ければ、関税率が高くても、実際の売上に対する税負担は相対的に軽くなるのです。
関税の“痛み”は確かにありますが、それは資金繰り面の一括負担においてであり、利益率への影響は必ずしも致命的ではない――そんな実感を持ったこともありました。
消費税は“平等”でも重い──売上に直接かかる重税感
一方で、消費税の“重さ”は違った形で感じられます。日本の消費税は、売上全体に対して10%が課税される仕組みです。
どれだけ利益率が低くても、売上100円に対して10円の税が必ず発生します。とくに食品小売のようにマージンが薄い業種では、消費税は直接的に利益を圧迫します。
表向きは「すべての製品に平等にかかる中立的な税」ですが、実際の商売においては、「売れば売るほど税が増える」という構造が、関税以上に厳しく感じられることもあるのです。
“不公平な優遇”? 輸出免税制度のジレンマ
消費税には、国際的に認められた仕組みとして「輸出免税制度」があります。これは、国内で生産された商品を海外に輸出する場合、その販売には消費税がかからず、仕入れ時に払った消費税も還付されるという制度です。
この制度自体は、WTOをはじめとした国際ルールでも「中立的な税制設計」とされています。国内消費にだけ税をかけ、国外消費には課税しないのは合理的とも言えるでしょう。
しかし実務の現場では、輸出企業がこの仕組みを活用することで、実質的に国内販売よりも優遇されているように見えるケースもあります。これが一部の国にとっては「見えない補助金」に映る要因でもあります。
トランプ大統領はなぜ消費税を批判しないのか?
トランプ大統領は、これまで「不公平な貿易慣行」に対して強く批判を行い、関税という手段で対抗してきました。しかし彼が消費税制度そのものを名指しで批判したことは、これまでほとんどありません。
その理由の一つは、WTOがVAT(付加価値税)を中立かつ合法と位置づけている点にあります。消費税制度を正面から批判すれば、アメリカ側が国際的に不利な立場に立たされる恐れがあるのです。
その代わりにトランプ大統領は、関税という“目に見える武器”で、「相手国が有利な制度を使っている」という不満に応える形をとっています。
制度は正しくても、現場は“重さ”を感じている
貿易制度や税制は、どれも理論上は公平かつ合理的に設計されています。消費税も関税も、それぞれ明確な目的と仕組みがあり、国際的にも整合性があると認められています。
しかし現場に立つと、それとは別の“重さ”を感じることがあります。関税の方が分かりやすい“壁”である一方、消費税は売上そのものに重くのしかかる“圧力”となり、利益をじわじわと削っていくのです。
制度上の“中立性”と、経営上の“実感”のズレ──このギャップこそ、制度議論において忘れてはならない視点だと感じます。
おわりに|貿易の“公正さ”を問い直すために
トランプ関税が支持される背景には、「制度的に不当だ」というよりも、「感情的に不公平に見える」制度構造への不満があるのかもしれません。
消費税の輸出免税、日本の高関税、アメリカにないVAT制度──それぞれの国の制度は、その国の事情に基づいて設計されています。しかし国境を越えた貿易の現場では、それらが“見えない不均衡”を生むこともあるのです。
制度の正しさと、現場の実感。その両方を踏まえて、これからの貿易のあり方を考える時期にきているのかもしれません。
【FPTRENDY内部リンク】
【外部関連リンク】
- 日本銀行(BOJ)公式サイト ─ 国内金利や政策決定の確認に。
- 米連邦準備制度理事会(FRB)公式サイト ─ FOMCや声明内容はこちら。
- Bloomberg(ブルームバーグ日本版) ─ 世界の金融・経済ニュースを網羅。
- Reuters(ロイター日本語版) ─ 最新のマーケット速報と経済記事。
- TradingView ─ 株価・為替・指数チャートの可視化に便利。