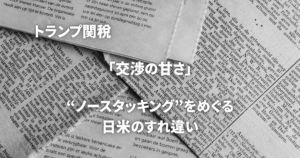2025年5月13日、日産自動車は2024年度通期決算と経営再建計画を発表した。最終損益は6,708億円の赤字に転落し、過去最大規模の赤字を計上。これを受け、国内外の工場削減や人員削減を含む大胆な構造改革策を打ち出した。
おしゃべりAI解説
2024年度(昨年度)の決算概要
2024年度の通期決算では、グループ全体の売上高が12兆6,332億円となり、前年同期に比べてわずか0.4%の減少にとどまりました。これは世界的な自動車需要の調整局面や為替変動を背景にした厳しい市況にもかかわらず、足元の販売が一定水準を保ったことを示しています。しかし一方で、自動車部品やアフターサービス収益の伸び悩みが全体の収益力を下押しし、規模面での保全には成功したものの、構造的な収益改善には至りませんでした。
営業利益は697億円にとどまり、前年度比で実に87.7%の大幅減少となりました。主力市場での価格競争激化や、新興国での販促コスト増加が重荷となり、従来の利益率を大きく下回る水準に沈み込みました。特に北米事業では新車投入による一時的なコスト嵩上げや、電動車シフトに伴う生産ライン改修費用が重くのしかかり、営業段階での収益力が著しく低下しました。
最終損益は▲6,708億円の巨額赤字となり、前年度の黒字から一転して過去最大級の赤字転落を記録しました。税引前利益の段階から大幅な落ち込みを見せ、評価損や為替差損も重なった結果、純利益ベースでの赤字幅が想定を大きく超えて膨らみました。この結果、自己資本比率の低下や資本政策の見直しを迫られる格好となりました。
主な赤字要因
- アメリカ市場を中心とした販売不振
米国市場では、競合他社の新型SUVやハイブリッド車との競争激化が続き、従来モデルの販売台数が計画を大きく下回りました。割安感を出すための値下げ策や販促キャンペーンを多用したものの、ブランドイメージ維持との両立が難航し、販売数量・収益ともに想定以下の結果となりました。 - 販売費・広告宣伝費の増加
電動化・デジタル化への対応を進める中で、製品訴求のためのマーケティング投資が急増しました。特にオンライン広告やSNSを活用したプロモーション、EV新モデルのローンチイベントなどに多額の予算を投入したことで、一時的に販管費がかさんで利益を圧迫しました。販売網再編に伴う販促支援費用も重なり、販管費率は前年から上昇しました。 - 国内外工場の資産価値見直しに伴う約5,000億円の減損損失
世界的な自動車需要の変動を受け、稼働率が低下した生産拠点の資産価値を見直し、大規模な減損処理を実施しました。特に欧州・アジアの数拠点で設備稼働率が落ち込み、帳簿価額と回収可能価額との差額として約5,000億円超を損失計上。この減損損失が一時的に赤字を押し上げる要因となりました。 - 生産能力過剰(能力500万台に対し実績304~310万台)
世界全体の生産能力は約500万台と大規模なキャパシティを有するものの、実際の生産はおよそ304万~310万台にとどまり、稼働率は60%台前半に落ち込みました。この余剰設備が固定費負担を増大させ、採算ラインを下げる結果に。今後、設備稼働率向上策や生産再編が急務となっています。
株価推移(チャート)
発表前後の市場の反応を示す、直近1年間の日足チャートを以下に掲載します。

図:FPTRENDY.COM TradingViewより取得(日足:2024年5月~2025年5月)
経営再建計画の主なポイント
1. 人員削減
過去に発表済みの9,000人削減計画に加え、今般さらに10,000人超の削減を実行することを決定しました。これにより、グループ全体の従業員数は約2万人分が削減対象となり、全社人員の約15%に相当します。削減スケジュールは2025年度から開始し、2027年度末までの3年間で段階的に実施。国内外を問わず、すべての事業拠点が見直し対象となります。
削減手法は自然減に加え、早期退職優遇制度や研修・再就職支援プログラムを併用し、人員整理の社会的影響を最小限に抑える方針です。特に国内従業員については、地域経済への配慮から、希望退職の募集や再配置を優先的に検討。期間中は専門のコンサルティングチームを設置し、個々のキャリア支援や生活設計のサポートを強化していきます。
一方で、削減後の組織体制は“スリムで強い日産”の構築を掲げ、事業部門の統廃合や管理部門のアウトソーシング推進によって、残存メンバーの裁量を増大。意思決定の迅速化と現場主義を徹底し、少人数体制で高い成果を出せる組織への転換を図ります。
2. 工場再編・生産能力適正化
現在17カ所ある製造拠点を、国内外合わせて10カ所へ大幅に集約します。すでにタイ現地の3工場閉鎖が表明されており、これに続き欧州や南米、中国などの主要拠点も含め、稼働実態に見合った再編計画を順次公表。2027年度までに生産キャパシティを従来の約350万台から250万台へと引き下げ、稼働率向上を目指します。
閉鎖・統合の基準は、①現地市場の需要動向、②工場稼働率、③コスト競争力、④設備老朽度――の4要素で評価を行い、効率性の低い拠点から段階的に廃止。統合先の工場には最新の生産ラインや自動化技術を投入し、1ラインあたりの生産性を大幅に向上させる計画です。
加えて、工場再編に伴う物流ネットワークの見直しを同時に進行。部品調達・完成車輸送の最適ルートを再構築することで、グローバル・サプライチェーン全体のリードタイム短縮とコスト削減を両立させる狙いです。
3. コスト構造改革
全社横断で5,000億円規模のコスト削減を来年度までに実現する目標を設定しました。主な施策として、購買部門の一元化による部品調達コストの引き下げ、管理部門のプロセス改革による固定費の圧縮、さらにIT・デジタル化による業務効率化を推進します。
具体的には、部品発注から在庫管理までを統合プラットフォームで管理し、発注量最適化と在庫回転率向上を図ります。同時に、バックオフィス業務についてはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入を加速し、年間数百人相当の定型業務時間削減を目指します。
また、研究開発費や販促費の投資判断基準を厳格化。ROI(投資利益率)が一定水準に達しないプロジェクトは見直し、得意分野に集中投資することで、限られた経営資源を高い成長ポテンシャル領域に再配分します。
4. 他社との協業強化
新たな競争優位を獲得するため、国内外の自動車メーカーや部品サプライヤーとの連携を深化させます。
- 三菱自動車工業 とは、PHEV(プラグインハイブリッド車)の供給契約を拡充。日産の国内工場を共同生産拠点として活用し、両社の生産効率向上とコストシナジー創出を目指します。
- ルノー や インド現地企業 との協業では、小型EVや商用車のプラットフォームを共有。製品開発・調達・販売の各フェーズで共同プロジェクトを推進し、グローバル規模での開発コスト低減を狙います。
- ホンダ とは、両社が2025年2月に統合協議を打ち切った後も、電動化や車載知能化(コネクテッドカー)分野での技術交流・共同研究を継続検討。市場投入の早期化と技術標準化を両立し、次世代モビリティ市場での競争力を高めます。
- アメリカ市場 では、関税引き上げの影響を受ける中で、日産の国内外工場の遊休設備を外部メーカーに提供するなど、新たな生産提携も模索。これにより、余剰生産能力の活用と関税コストの一部軽減を狙います。
以上の再建策を通じて、日産自動車は「効率性」と「革新性」を両立させた新たなビジネスモデルへの移行を図ります。三位一体の構造改革が成果をあげられるかが、今後の業績回復の鍵となるでしょう。
社長コメントと過去の教訓
2025年2月に社長に就任したイヴァン・エスピノーサ氏は、記者会見の冒頭で「日産の業績回復は待ったなしの課題であり、現状の赤字体質から一刻も早く脱却しなければならない」と強く訴えました。さらに「これまでの延長線上では再建は成し遂げられない。大胆かつ踏み込んだ施策を迅速に実行に移し、会社の体質を根本から変える必要がある」と、従来の枠にとらわれない改革姿勢を鮮明に示しました。エスピノーサ社長は特に「スピード感」を重視し、意思決定の迅速化と現場への権限委譲を通じて、計画策定から実行までのタイムラグを極小化する考えを示しています。
こうした強いリーダーシップ表明の背後には、日産が過去に直面してきた再建の“光と影”の経験があります。まず、1990年代初頭のバブル崩壊後、当時の経営陣は複数の国内外工場を閉鎖し、大規模な人員整理を実施して損益分岐点を下げ、短期的には黒字転換に成功しました。また、2019年度にはカルロス・ゴーン体制下で推進された再建策として、事業部門の集約や生産ラインの統合を断行し、約1兆円規模のコスト削減を達成。これにより一度は黒字化を果たしました。
しかし、その後の業績回復局面では、「量的拡大」に振れすぎたあまり、生産設備を過剰に拡大してしまった反省点もあります。需要回復を見越して増強した生産キャパシティが、実際の販売動向を上回るペースで稼働率低下を招き、固定費負担を重くした結果、再び業績の足を引っ張る要因となりました。エスピノーサ社長はこの教訓を踏まえ、今回の再建では「量から質への転換」をキーワードに掲げ、単なる生産台数の追求ではなく、一台当たり利益の最大化と機動的な生産体制を追求する方針です。
そのうえで社長は、「過去の成功体験に固執せず、失敗から学びを得ることが真の強さを生む」と強調。社員一人ひとりに対して「現場の声を徹底的に聴き、現状の課題を自らの手で解決してほしい」と呼びかけ、トップダウンのみならず、ボトムアップの改革も同時に推進する意向を示しました。これまでの「赤字を脱するための再建」から一歩進んだ、「持続的成長を見据えた企業体質の変革」への転換が、日産にとって今まさに求められていると言えるでしょう。
今後の焦点
今回発表された大規模な再建策は、これまでの日産が培ってきた成功体験と、その反省に基づく“大胆な構造改革”の集大成ともいえます。しかし、策の規模・速度感・複雑性を考えると、実際に成果を上げるためには以下のポイントに最大限の注意を払う必要があります。
- 人員削減の実行と定着
グループ全体で約2万人分、従業員の約15%を削減する計画が、2027年度末までに段階的に実施されます。希望退職から再配置支援まで多彩な施策を用意しているものの、実際に“適切な人材配置”と“組織風土の維持”を両立させるのは容易ではありません。国内外を問わず従業員の仕事・キャリア設計に与える影響は大きく、労働組合や地方自治体との調整、社内コミュニケーションの透明性をいかに保つかが、現場の士気維持と計画のスムーズな進行に直結します。 - 工場再編の成否と生産効率
現行17工場から10工場への統合・閉鎖計画では、特に稼働率の低い拠点を対象に、生産ラインや自動化設備への再投資をセットで検討。タイの3工場閉鎖に続き、欧州・中国など主要地域の拠点見直しが控えています。工場間の統合スケジュール、設備移設コスト、新旧拠点の生産切り替えタイミングを綿密に管理しないと、一時的なライン停止や納期遅延を招きかねません。生産キャパを350万台→250万台へ調整する計画が、実際に効率改善に結び付くかが最大の焦点です。 - 財務改善と短期収益へのインパクト
減損損失計上による資本効率悪化を改め、5000億円規模のコスト削減と人員・工場再編のシナジー効果で、2026年度には営業黒字化を目指します。株主や債権者は、四半期ごとのKPI(人件費率、工場稼働率、営業利益率など)を注視。計画の途中段階で数値目標を達成できない場合、資金調達コストの上昇や格付け機関からの格下げリスクが高まる可能性があります。 - 外部ステークホルダーの視線
政府(経済産業省)、労働組合、地方自治体、取引金融機関は、2万人規模の削減が地域経済や雇用に与える影響を細かく点検。特に国内工場閉鎖による雇用喪失リスクや下請けサプライヤーへの波及効果を注視しており、日産が地域社会への説明責任を果たせるかが、行政支援や補助金交付などの後押しを得られるかどうかに影響します。 - 長期的競争力と持続的成長
短期収益回復だけでなく、電動化・デジタル化時代に即した商品ラインアップの刷新、新技術への投資、そして他社協業によるプラットフォーム共有が、5年後・10年後の日産の競争ポジションを左右します。人員・工場再編で浮いた経営資源を、EVやコネクテッドカーといった将来投資に適切に振り分けられるかが、構造改革の“本当の成果”を決定づけるでしょう。
――市場は、これら全要素が「計画どおりに」かつ「バランスよく」実行されるかを見極めています。日産が持続的な収益性と技術革新を同時に実現し、株主価値の回復を果たせるかが、当面の最大の注目点です。
関連リンク:
- 日本銀行(BOJ)公式サイト ─ 国内金利や政策決定の確認に。
- 米連邦準備制度理事会(FRB)公式サイト ─ FOMCや声明内容はこちら。
- Bloomberg(ブルームバーグ日本版) ─ 世界の金融・経済ニュースを網羅。
- Reuters(ロイター日本語版) ─ 最新のマーケット速報と経済記事。
- TradingView ─ 株価・為替・指数チャートの可視化に便利。